立ち灯籠
立ち灯籠は、基本的には上から「宝珠(玉)」「笠」「火袋」「受け(中台)」「柱(棹石)」「地輪(台座、基礎)」で構成される灯籠の事を差します。
台座部分が無い、柱を地面に埋めて立てるものは「生け込み(活込み)灯籠」になります。
寺社での灯り用に作られた事から始まり、武家社会となった鎌倉時代に大いに発展しました。
この時代に多くの銘品が存在しますが、これは加工技術の進歩や、有力者が寺社に寄進するようになったからと言われています。
 とても種類も数も多いので、掲載しているのは在庫の中の一部です。お探しの灯籠などがございましたら御一報下さい。
とても種類も数も多いので、掲載しているのは在庫の中の一部です。お探しの灯籠などがございましたら御一報下さい。
また、掲載された灯籠類については岡崎で加工された事を証明する岡崎製造証明書を発行できます。
ご注文時にお申し付けくだされば発行いたします。
岡崎産の石材で制作した場合は、石材の産地証明も発行できます。詳しくはお問合せください。
商品紹介
各商品の小さい写真、もしくは品名をクリックすると拡大写真が表示されます。
名前から探したい時はページ末尾の「
掲載中の立ち灯籠の一覧」から探せますのでご利用ください。
伝統的工芸品に指定された灯籠 (基本的な灯籠)
本歌は東京の赤坂御苑にあり、東宮殿下のご成婚を記念して岡崎から献上されたものです。この灯籠は近年の生まれたものと言えます。
石灯籠の中の模範となるべく、数々の国宝級の灯籠をベースにして造られました。
石灯籠の中の模範となるべく、数々の国宝級の灯籠をベースにして造られました。
本歌は春日神社の中にあり、社伝によれば保延三年、摂政藤原忠通公が飢饉を憂いてこの灯籠を寄進し、柚の木の下に据えて御祭りした事から、その名がついたそうです。
特徴はそのエンタシスのついた柱と、笠から中台(受け)までは8角、柱は円で、基礎が6角、というのは他の灯籠には見られない点です。全体的にすっきりとした印象。
特徴はそのエンタシスのついた柱と、笠から中台(受け)までは8角、柱は円で、基礎が6角、というのは他の灯籠には見られない点です。全体的にすっきりとした印象。
宇治の平等院鳳凰堂の前に本歌があります。火袋が一個石ではなく、2枚の板石を立てたもので、他の灯籠には無い特徴です。
平安時代のものと思われますが、中台から上は江戸時代に作り直されたもので、本来の形は分かっていません。
平安時代のものと思われますが、中台から上は江戸時代に作り直されたもので、本来の形は分かっていません。
よく見かけるのは左のぽっちゃりした(?)善導寺型ですが、本歌に近いのは右のすっきりしたほうです。
なぜ間違った形のほうをよく見かけるのかと言うと、その昔、 岡崎の職人が伝聞で作った善導寺型が各地に広まってしまったため、だそうです。
なぜ間違った形のほうをよく見かけるのかと言うと、その昔、 岡崎の職人が伝聞で作った善導寺型が各地に広まってしまったため、だそうです。
それ以外の灯籠
愛知県幡豆町の糟谷邸という旧家に本歌があります。
比較的新しい灯籠(江戸時代)なので、オリジナルとほぼ同じ形に造る事ができました。
比較的新しい灯籠(江戸時代)なので、オリジナルとほぼ同じ形に造る事ができました。
京都の青蓮院(岡崎の職人は「せいれいいん」と呼びますが、正しくは「しょうれんいん」)の中に本歌があります。
院内の好文亭という茶室の貴人口前に、蹲踞(つくばい、水鉢)の鉢明りとして据えられています。この蹲踞と、書院の縁先にある一文字形水鉢が有名です。
院内の好文亭という茶室の貴人口前に、蹲踞(つくばい、水鉢)の鉢明りとして据えられています。この蹲踞と、書院の縁先にある一文字形水鉢が有名です。

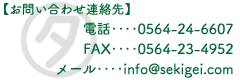
 メールで問い合わせる
メールで問い合わせる
























































ですが、実際に本歌(オリジナル)と言われていいる物は、あまりにも古過ぎて原形が分からず、この写真とは大きく異なります。おそらく時代を経るうちに、本来の春日とは変わっていってしまったものの、新しい春日型の方が有名になってしまったのでしょう。